
賃貸物件から引っ越しをする際「賃貸の退去費用はいくらかかるんだろう?」と不安に感じたことはありませんか?
実際、独立行政法人国民生活センターでは賃貸の退去費用に関するトラブルの相談が後を絶たず、2024年には年間で13,277件の相談が寄せられています。
そこで本記事では、賃貸の退去費用や退去費用を安く抑えるポイントについて詳しく解説いたします。
この記事を読めば、賃貸を退去する際の費用に関する不安を解消できます。
賃貸の退去を考えている方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
賃貸の退去費用ってそもそも何?

賃貸の退去費用とは、賃貸物件を退去する際に入居者が支払う費用の総称で、”物件を次の入居者が住める状態に戻す”ために必要な費用です。
賃貸の退去費用の内訳は、主に以下の3つです。
- 原状回復費用
- ハウスクリーニング費用
- その他の費用(残置物処分費用、事務手数料など)
賃貸の退去費用は、入居時に預けた敷金から差し引かれるのが一般的です。
退去費用が敷金では足りない場合は追加請求、余った場合は敷金の残りが返還されます。
入居時に敷金なしの物件では、退去時に直接退去費用が請求されるという点に注意しましょう。
賃貸の原状回復義務って?
原状回復義務とは、賃貸借契約が終了した際に”借主が物件をもとの状態に戻す義務”のことです。
これは民法にも規定されており、法律上の義務として位置付けられています。
退去費用の中心となるのが、原状回復義務による「原状回復費用」です。
これは”賃貸物件を入居時の状態に戻すためにかかる費用”を指します。
原状回復義務で重要なのは、「すべてのキズや汚れを直す必要はない」という点です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、費用負担について明確に区分されています。
入居者が負担するもの
- 故意や過失による損傷:壁に釘を打った穴、飲み物をこぼして放置したシミ、家具を引きずってできた深いキズなど
- 通常使用を超える損傷:タバコのヤニ汚れ、ペットによる引っかきキズ、子どもの落書きなど
- 管理不足による損傷拡大:水濡れを放置して腐食が広がった、カビを放置して壁紙の全面張り替えが必要など
大家が負担するもの
- 経年劣化:日照による壁紙の変色、畳の日焼け、設備の自然故障など
- 通常使用による損耗:家具設置による床のへこみ、壁の画びょう穴(下地のボード張り替えが不要な程度)、テレビ裏の電気焼けなど
簡単にまとめると、入居者の行動や管理不足が原因の損傷は入居者負担、普通に生活していて自然に発生する損傷は大家負担ということになります。
フローリングのキズは補修が必要?
フローリングの損傷を例に、入居者負担になるのか大家負担になるのかを確認してみましょう。
入居者負担となるフローリングの損傷
- 重い物を落として深くえぐれたキズ
- 家具を引きずって広範囲にできたキズ
- 飲み物をこぼして放置し、板が反った部分
- ペットが引っかいてできたキズ
大家負担となるフローリングの損傷
- 家具の重みによる自然なへこみ(通常使用の範囲内)
- 経年による小さな擦りキズや色あせ
- 歩行による自然な摩耗
さらに重要なのが「減価」の考え方です。
賃貸物件の設備や内装は時間と共にその価値が減少します。
これを「減価」といい、通常の利用による減価分については入居者が原状回復費用を負担する義務が生じません。
国土交通省が作成した「原状回復ガイドライン」では、フローリングについて、”補修は経過年数を考慮しない。フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような負担割合を算定する。”とされています。
例えば、木造アパートの建物耐用年数を22年と仮定した場合、フローリングも同じ22年が基準となり、1年間で約4.5%ずつ価値が下がっていきます。
入居時にフローリングが新しく張り替えられていた場合、入居して5年が経過した木造アパートで退去時に全面張替えを行うと、残存価値に基づき賃借人が負担すべき割合は(22年 − 5年) ÷ 22年 ≒ 77.3%となります。
一方、入居時点ですでにフローリング張替えから5年が経過していた場合、入居して5年後には張替えから10年が経過していることになります。
この場合の残存価値は(22年 − 10年)÷ 22年 ≒ 54.5% となり、入居者の負担割合もそれに応じて小さくなります。
つまり、フローリングなどの設備が古くなるほど、入居者の修繕費負担は小さくなる仕組みです。
ただし、賃借人の故意・過失による損傷で、フローリングなどの長期使用に耐える部位を「部分補修」する場合は例外です。
この場合、国土交通省のガイドラインでは経過年数(入居年数)を考慮せず、部分補修の実費を賃借人が負担することになっています。
退去時にフローリングの修繕請求を受けたら、以下の点を必ず確認しましょう。
- 建物耐用年数
- 入居年数
- 部分的な補修か全面的な張替えか
- 損傷の原因(通常損耗か、故意・過失か)
また、賃貸借契約書に別途条件が記載されている可能性もあるので、事前に原状回復条件がどのように設定されているのかを確認しておきましょう。
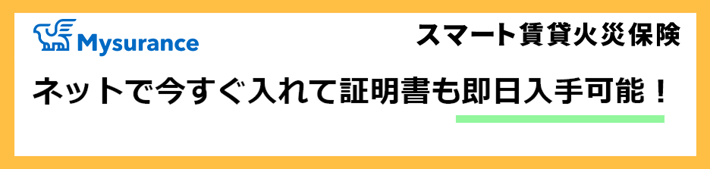
賃貸退去費用の相場はどれくらい?
退去費用の相場は、物件の広さや居住年数、補修の有無、地域等によって大きく変動します。
一般的な退去費用の相場は以下の通りです。
間取り別の基本相場
|
間取り
|
相場
|
|
ワンルーム・1K
|
1万5000円-3万円
|
|
1DK・1LDK
|
2-5万円
|
|
2DK・2LDK
|
3-8万円
|
|
3DK・3LDK
|
5-10万円
|
|
4DK・4LDK
|
9万円以上
|
地域差も考慮が必要で、首都圏では上記相場と比較して高額になる傾向があり、地方都市では安価になる傾向にあります。
賃貸の退去費用と火災保険の関係について

原則、退去費用(経年変化や原状回復費用など)は火災保険で補償されるものではありません。
ただし、賃貸物件で「偶然の事故」により大家さんに損害を与えてしまった場合には、火災保険に付帯する「借家人賠償責任保険」が適用され、補償対象となることがあります。
借家人賠償責任保険は、火災や水漏れなどの突発的な事故によって建物に損害を与え、入居者が法律上の損害賠償責任を負った際に、その費用を補償する保険です。
一方で、経年劣化や通常使用に伴う損耗、また入居者の故意による損傷などは対象外であり、すべての損傷が保険で補償されるわけではない点に注意が必要です。
借家人賠償責任保険について知っておきたいこと
借家人賠償責任保険が利用できるのは、あくまで「偶然の事故」によって損害が生じた場合に限られます。
具体的な事故例は、以下の通りです。
1. 水漏れ事故
2. ボヤなどの火災事故
3. 破裂・爆発事故
借家人賠償責任保険では、「通常損耗」や「経年劣化」は補償対象外となります。
また、損傷の発生から時間が経過してしまうと、偶然の事故であることの証明が難しくなり、損傷日時が曖昧になることで保険適用にならない可能性が高くなる点に注意が必要です。
万が一事故が発生した場合は、できるだけ早く損傷の状況を写真で記録し、契約している保険会社へ連絡しましょう。
借家人賠償責任保険について、さらに詳しく確認したい方は以下の記事を確認してみましょう。
借家人賠償責任保険とは?自分で選ぶときの注意点について解説
賃貸の退去費用を抑える5つの予防策

賃貸の退去費用をできるだけ安く抑えるには、日常の生活や入居時から予防策を実践しましょう。
入居時や日常生活から気をつけておくべきポイントは以下の5つです。
1. 入居時の記録を徹底する
2. 水回りの管理をする
3. 壁や床をキズつけないように工夫する
4. 設備や機器をメンテナンスする
5. 禁煙・ペット関連の対策をする
これから賃貸への入居予定がある場合は、入居時にキズや損傷の写真を撮影しましょう。
入居時に既にあったキズや汚れを見落とすと、退去時に自分の責任にされてしまう可能性があります。
水回りや壁、床、設備などは退去費用に繋がりやすい箇所です。
定期的に清掃やメンテナンスを行い、退去費用を削減しましょう。
また、タバコのヤニ汚れや、ペットによる爪とぎキズなどは、修理費用が高額になりやすいです。
室内では禁煙し、ペット対策には爪とぎ防止シートなどを活用し、退去費用を出来るだけ抑えましょう。
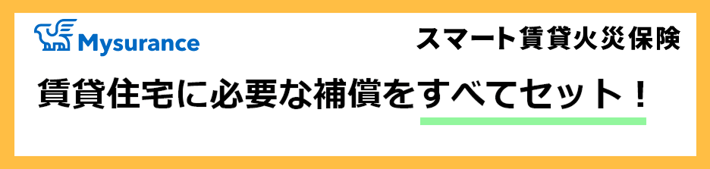
まとめ:賃貸の退去費用は削減できる可能性がある

今回の記事では、賃貸の退去費用について詳しく解説いたしました。
この記事の内容のまとめは以下の通りです。
- 賃貸の退去費用とは”物件を次の入居者が住める状態に戻す”費用
- 通常損耗や経年劣化に対して、原状回復義務はない
- 日常の生活や入居時からの予防策を実践する
退去費用は賃貸を利用する上で避けては通れないものですが、正しい知識と適切に予防をすれば、大幅に軽減できます。
特に水漏れや偶然な事故による損傷は、保険適用の可能性もあるので、事故が起きたらすぐに契約している保険会社へ連絡しましょう。
適切な対応をして、退去時の経済的な負担を最小限に抑えましょう。
MYS25-100314

